EPPとは?主な機能やEDRとの連携の重要性、EPP製品の選び方を解説
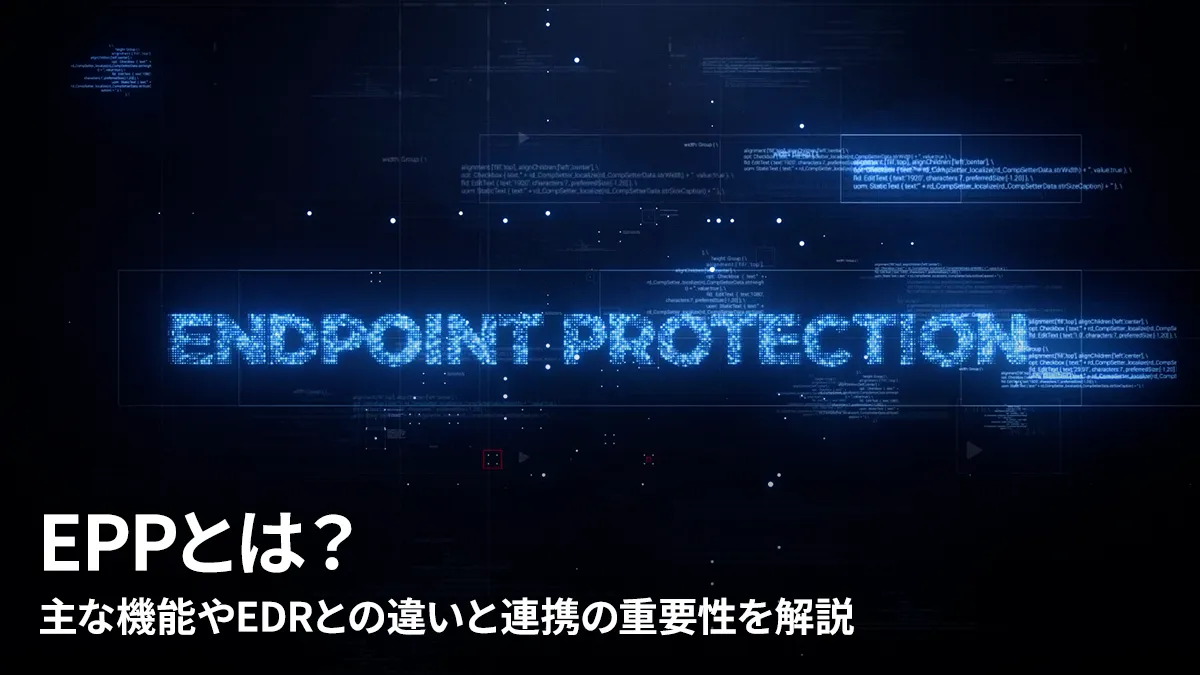
近年、エンドポイントセキュリティの重要性が高まる中で、注目されているのがEPP(Endpoint Protection Platform)です。EPPは、ウイルスやマルウェア、不正アクセスなど多様な脅威からPCやスマートフォン、サーバーなどの端末を保護するための包括的なセキュリティソリューションを指します。
従来のウイルス対策ソフトではカバーしきれなかった、予防・検知・対応の全フェーズを一貫して提供できる点が、EPPの大きな特徴です。また、EPPは次世代アンチウイルス(NGAV)やエンドポイントで脅威の検知と対応を行う仕組みであるEDR(Endpoint Detection and Response)と連携し、さらにセキュリティ専門組織による監視・分析体制のSOC(Security Operation Center)と統合運用することで、より高度な防御体制の構築が可能となります。
本記事では、EPPの基本的な機能と仕組み、EDRとの連携の重要性、導入メリットなどを解説します。EPP導入を検討中の企業担当者・IT管理者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
EPPとは、エンドポイントをサイバー攻撃から保護するためのセキュリティソリューション
EPPとは、PC、スマートフォン、サーバーなどのエンドポイントを対象に、ウイルスやマルウェア、不正アクセスなどのサイバー攻撃から保護する包括的なセキュリティソリューションです。
従来のウイルス対策ソフトは、既知のウイルスを検知して駆除する「検知と除去」を中心としていましたが、EPPはそれに加え、攻撃を未然に防ぐ「予防」や、万一の侵入に備えた「対応」までをカバーしています。また、EPPはファイアウォール機能や侵入検知・防止機能、アプリケーション制御、次世代アンチウイルスなどを統合的に提供し、エンドポイントの安全性を多層的に保護します。特に、サイバー攻撃の起点となりやすいエンドポイントを守ることは、全社的なセキュリティリスクを軽減する上で重要です。
企業のIT環境がクラウド化やモバイル化によって複雑化している現在、EPPの導入は企業にとって不可欠なセキュリティ対策とされており、情報漏洩、システム停止など重大なセキュリティインシデントの防止に役立っています。
EPPの重要性とその背景
近年、サイバー攻撃は日々高度化・巧妙化しており、企業にとって深刻な脅威となっています。特に、攻撃者が最初に狙う従業員が使用するPCやスマートフォンなどのエンドポイントは、脆弱性を突かれやすい箇所です。そのため、エンドポイントをサイバー攻撃から保護するEPPの重要性は一層高まっています。
多くのサイバー攻撃は、メールの添付ファイルやWeb閲覧など、日常的な操作を起点に始まります。これにより、従来の境界型セキュリティ(ネットワークの出入り口に防御を集中させる方式)だけでは十分に対処できない状況となっており、EPPによる端末レベルでのリアルタイムな防御が不可欠です。
さらに、テレワークの拡大や私物端末の業務利用の普及により、企業内のエンドポイント環境では、多様化・分散化が進んでいます。こうした背景を受け、EPPは多様なリスクに対応できる柔軟かつ包括的な機能が求められており、企業が安全にビジネスを継続するために欠かせない存在となっているといえるでしょう。
最近では、クラウド型EPPやAIを活用した脅威検知機能を備えた製品の普及も進み、従来のセキュリティ製品と比べて導入・運用の負担が少ないことから、中小企業を中心に導入が進んでいます。また、「すべてのアクセスを信頼しない」ことを前提とするゼロトラストの考え方と連携したセキュリティモデルの中でも、EPPは中核的な役割を担う存在として位置付けられており、今後さらに市場の拡大が見込まれています。
ゼロトラストについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
EPPの主要機能と仕組み
EPPは、さまざまなサイバー脅威に対応するための多機能型セキュリティプラットフォームです。従来のウイルス対策にとどまらず、複数のセキュリティ機能を一元的に提供することで、エンドポイントを多層的に保護します。
ここでは、EPPに搭載されている主な機能として以下の3つについて解説します。
- ウイルス・マルウェア対策
- 侵入検知・防止
- レスポンス機能(EDR連携)
ウイルス・マルウェア対策
EPPの主要機能の1つは、ウイルスやマルウェアへの対策です。
既知の脅威だけでなく、未知のマルウェアに対しても、次世代アンチウイルスを活用することで、検知と排除を可能にします。具体的には、AIや機械学習による振る舞い分析によって、ファイルの挙動やプロセスをリアルタイムで解析し、従来のシグネチャベースでは見逃されがちなサイバー攻撃も早期に検知できます。シグネチャベースとは、過去に判明したマルウェアの特徴と一致するかで脅威を検出する手法です。一方、振る舞い分析とは、プログラムの実行中の動作やネットワーク通信、システムへの変更などを監視し、通常とは異なる不審な挙動を検出する技術を指します。これにより、未知のマルウェアにも柔軟に対応できます。
さらに、ファイアウォール機能も併せ持ち、外部からの不正アクセスや不審な通信をブロックし、ネットワーク経由のサイバー攻撃の侵入口を封じることが可能です。
侵入検知・防止
EPPの主要機能には、異常な通信や挙動をリアルタイムで監視する侵入検知・防止が含まれており、攻撃の兆候を即座に検知・遮断します。
また、デバイス制御機能により、USBメモリや外付けHDDなどの外部記憶装置の利用を制限・管理し、内部からの情報漏洩、マルウェアの持ち込みを防ぎます。こうした機能は、リモートワークやモバイルワークが増える中で、管理者の目が届きにくいエンドポイントの保護において特に有効です。
レスポンス機能(EDR連携)
EPPの主要機能として、レスポンス機能(EDR連携)も挙げられます。
サイバー攻撃は、完全に防ぐことは難しいため、被害を最小限に抑える対応(レスポンス)も重要です。EPPでは、EDRと連携することで、万が一サイバー攻撃を受けた際にも迅速な対応を可能にします。EDRは、セキュリティインシデント発生時にその原因を追跡・分析し、範囲や影響を特定します。これにより、被害拡大を防ぐための隔離措置や除去対応を迅速に実施できます。
EPPとEDRを組み合わせることで、「予防」から「検知」「対応」までを一貫してカバーする統合的なセキュリティ体制を構築でき、業務停止や情報漏洩といった重大リスクへの備えを強化できるでしょう。
EDRについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
EPP製品の比較と選び方
EPPは、企業の端末をマルウェアや不正アクセスから守るための入口防御の基盤です。製品選定では、個別機能の優劣を見るだけでなく、企業の環境や運用体制とどれだけ適合するかが重要になります。ここでは、EPP選びで重視される項目を整理します。
ニーズとの適合度
最も重視すべきは、自社のニーズと製品がどれほど合致しているかという点です。業務上扱うデータの種類や機密性、リモートワークの比率、社内のITリテラシーや運用体制などにより、求めるセキュリティレベルや管理機能は大きく変わります。また、業界固有のガイドラインやコンプライアンス要件に対応できるかどうかも判断材料になります。単に「高機能だから安心」という視点ではなく、自社のリスク特性に対して過不足なくフィットしているかを見極めることが、導入後のトラブルを防ぐうえで不可欠です。
検知方式
EPP の検知方式には、シグネチャを中心にした従来型のモデルから、AI や機械学習、振る舞い分析を用いた次世代型まで幅があります。現在は未知の脅威やファイルレス攻撃が増えており、静的なパターン照合だけでは十分に防ぎきれないケースも少なくありません。そのため、製品ごとにどのような手法を組み合わせているのか、未知系の攻撃にどこまで対応できるのか、誤検知の傾向やアラートの精度はどうかといった点を確認することが重要です。検知方式は製品の思想に直結する領域であり、この違いが運用時の負担や検知結果の質に大きく影響します。
対応OS・運用負荷
導入後の扱いやすさを左右するのが、対応OSの幅と運用負荷です。Windows中心の環境であれば多くのEPPが対応できますが、MacやLinux、サーバー、VDIなどが混在する環境では製品ごとにサポート範囲の差が出やすくなります。また、エージェントの更新しやすさ、管理コンソールの使い勝手、ポリシー配布の容易性、アラートの量や質といった要素は、日々の運用工数に直結します。特に誤検知が多い製品は対応に追われやすく、セキュリティ担当者の負担が増える原因になります。長期的に安定運用できるかどうかを見極めるためにも、PoC や試験導入で実際の操作感やアラート特性を確認しておくことが望ましいと言えます。
| 製品名 | ベンダー | 検知方式の要点 | 対応OS | EDR/XDR連携 |
|---|---|---|---|---|
| SentinelOne Singularity EPP | SentinelOne | AIベースの防御にEPPとEDRを統合可能 | Windows macOS Linux | Singularity XDRで相関分析 |
| Trend Micro Apex One | トレンドマイクロ | 多層防御。EPPを土台にEDRやXDRとも連携可 | Windows macOS(サーバー版は別ライン) | Trend Vision OneでEDR/XDR連携 |
| Microsoft Defender for Endpoint | マイクロソフト | 予防 防御 検出 調査 対応を統合。Microsoftスタックと高親和 | Windows macOS Linux | Microsoft Defender XDRと密連携 |
| Symantec Endpoint Security | ブロードコム | クラウド ハイブリッド オンプレに対応する統合EPP | Windows macOS Linux | 自社EDR群と統合可 |
| Sophos Intercept X Endpoint | ソフォス | ディープラーニングとエクスプロイト対策。XDRやMDRへ拡張可 | Windows macOS Linux | Sophos XDR MDRと連携 |
EPPは入口防御の土台であり、製品選定では機能の多寡だけでなく、価格モデル、検知方式、対応OSや展開条件、日々の運用負荷、EDRとの連携度を総合的に見ることが重要です。ここでは比較の軸と判断ポイントを整理します。
まず価格は、ユーザー数や端末数にプラン機能とアドオンを掛け合わせた積み上げで決まるケースが多いです。ログ保管期間や高度な振る舞い検知、サンドボックス、脅威インテリジェンスの更新頻度などで単価が変動するため、三年TCOでの比較が現実的です。次に検知方式は、シグネチャだけでなく機械学習やヒューリスティック、振る舞い分析をどの程度組み合わせているかが要点です。未知系やファイルレス攻撃、正規ツール悪用の検知力は、テスト環境で必ず確認しておきたいところです。
対応OSと展開性では、Windows、macOS、Linuxに加え、サーバーやVDI、オフライン端末、OT環境への適用可否を確認します。インストールやポリシー配布、バージョン管理の自動化度合いが高いほど、運用のブレを抑えられます。運用負荷は、誤検知率とアラートノイズ、ルール作成の難易度、レポートや監査ログの検索性が実感差を生みますので、パイロット時に月次の対応時間を計測しておくことをおすすめします。
最後にEDRとの連携では、アラート相関や隔離コマンドの連携可否、APIやSIEM連携の深さを確認します。入口でのブロックに加え、侵入後の封じ込めと原因分析までを一連で回せる構成にすると、インシデント対応の速度と確度が上がります。以上の軸をチェックリスト化し、必須連携のカバー率と三年TCO、社内運用体制との適合度で比較すれば、導入後の想定外コストと運用リスクを抑えられます。
従来型アンチウイルス(AV)と次世代アンチウイルス(NGAV)の違いと進化
サイバー攻撃の手口は日々進化しており、従来型アンチウイルス(AV)だけでは対応しきれないケースが増えています。こうした背景を受けて登場したのが次世代アンチウイルス(NGAV)です。2つの主な違いとして下記の内容が挙げられます。
従来型アンチウイルスと次世代アンチウイルスの違い
| 従来型アンチウイルス(AV) | 次世代アンチウイルス(NGAV) | |
|---|---|---|
| 主な検知手法 | シグネチャベース | 行動分析・AI・機械学習 |
| 技術の特徴 | データベースと照合して一致を検出 | 挙動やパターンをリアルタイムで解析 |
| 対応範囲 | ファイル単位のスキャン中心 | ファイル、プロセス、ネットワークなど多層で監視 |
ここでは、下記の2つの視点から従来型アンチウイルスと次世代アンチウイルスについて詳しく解説します。
- 従来型アンチウイルスの限界
- 次世代アンチウイルスの特徴
従来型アンチウイルスの限界
従来型アンチウイルスは、あらかじめ登録されたマルウェアのシグネチャを使ってファイルをスキャンし、該当する脅威を検出・除去する手法です。この手法は既知のウイルスに対して高い効果を発揮します。
しかし、サイバー攻撃は日々新たな手口が生まれており、従来型アンチウイルスでは未知のマルウェアや巧妙にカモフラージュされた攻撃への対応は難しいという課題があります。特に深刻なのが、パッチ未公開の脆弱性を突いたゼロデイ攻撃です。これに対しては、シグネチャが存在しないため防御が困難であり、企業における情報漏洩やシステム停止など深刻な影響を及ぼす可能性があります。
このように、従来型アンチウイルスには防げる脅威の範囲に制約があるため、企業のセキュリティ対策としては補完的な手段にとどまるケースが増えています。
次世代アンチウイルスの特徴
次世代アンチウイルスは、従来型アンチウイルスの課題を克服するために開発された最新のセキュリティ技術です。AIや機械学習を活用した行動分析により、マルウェアの未知の挙動、不審なパターンをリアルタイムで検知します。
次世代アンチウイルスの大きな強みは、脅威の振る舞いに着目する点です。例えば、ファイルが暗号化されたり、外部に大量のデータが送信されたりするような動作を検出し、該当するファイルが過去に確認されていない場合でも、危険と判断して自動的にブロックします。
また、ネットワークトラフィックの監視などを通じて、多層的に検知することで、従来型アンチウイルスでは検知できなかったサイバー攻撃にも対応可能です。これにより、企業は進化し続けるサイバー攻撃に対して、より柔軟かつ効果的な防御策を実施できるでしょう。
アンチウイルスとEDRの違い
アンチウイルスとEDRの違いは、脅威への対処方法です。アンチウイルスは「侵入を防ぐこと」に重点を置き、EDRは「侵入された後の対処」に重点を置いています。
従来型アンチウイルスや次世代アンチウイルスは、主にマルウェアなどの脅威がエンドポイントに侵入する前に防御する「侵入防止」の役割を担っています。これらは、パターンマッチングや機械学習などの技術を活用し、マルウェアの書き込み時に検知・ブロックする仕組みです。
しかし、高性能なアンチウイルスであっても、すべての脅威を完全に防ぐことはできません。特に近年、従来の検知技術をすり抜ける巧妙な手口が増えており、「侵入を前提とした対策」が求められるようになっています。
そこで重要となるのが、EDRの導入です。EDRは、エンドポイントで実行される通信やプログラムの起動、認証情報の利用、OS設定変更、コマンド実行などの「振る舞い」を常時監視し、異常を検知・防御します。アンチウイルスが「侵入させない仕組み」であるのに対し、EDRは「侵入された後でも被害を防ぐ仕組み」です。
高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対して、アンチウイルスだけでは不十分といえます。EDRの導入によって、侵入後の攻撃活動を早期に察知し、迅速に対応することで、被害を最小限に抑えるセキュリティ体制を構築できるでしょう。
「EDRまで必要なのか分からない」「サイバー攻撃に本当に対応できる体制が整っているのか不安」と感じていませんか?「SentinelOne」なら、EPPとEDRの両機能を統合し、既知・未知の脅威に一貫して対応可能です。エンドポイントセキュリティの見直しやゼロトラスト環境への導入の第一歩として、ぜひご検討ください。
EPPとEDRの連携は重要
EPPとEDRは、それぞれ異なるセキュリティ課題に対応する役割を持ちつつ、連携させることで、企業の防御体制を飛躍的に強化できます。単体での導入よりも、両者を組み合わせた多層防御により、未知・既知を問わず脅威に対応する強固な対策が可能です。
EPPは、エンドポイントへのサイバー攻撃を未然に防ぐ「入り口対策」として機能し、EDRは、侵入後に発生する不審な挙動や異常な通信を監視・分析して必要に応じて隔離・削除を行う「出口対策」として機能します。これにより、1つのセキュリティ機能ではカバーしきれないリスクに対し、相互補完的に対応できる点が大きな特徴です。
特に、ランサムウェアのような高度なサイバー攻撃は、1つのセキュリティ対策だけでは完全に防ぎきれないことも多く、EPPとEDRの連携が大切になります。複数の機能を組み合わせた多層防御は、脅威の侵入・拡大・再発を防ぐ効果的なアプローチとされています。
企業にとっては、EPPとEDRを一体的に運用することで、セキュリティの抜け穴を減らし、全社的なリスク管理体制の強化が可能です。単体での製品導入にとどまらず、セキュリティ戦略全体において両者の連携を前提とした設計が不可欠といえるでしょう。
SOCとの連携による実用的なセキュリティ強化
EPPとEDRの連携によってエンドポイントのセキュリティ体制は大きく向上しますが、近年のサイバー攻撃はさらに高度化・巧妙化しており、それだけでは十分に対応しきれないケースも見られます。こうした複雑な脅威に対処するために重要となるのが、SOC(Security Operation Center)との連携です。
SOCは、企業全体のITインフラを対象に、24時間365日体制でセキュリティ監視を担う専門組織を指します。EPPはマルウェアの侵入を防ぎ、EDRは侵入後の不審な挙動を検知・対応しますが、その膨大なログやアラートを分析・判断し、的確に対応するには、高度なセキュリティの専門知識が求められます。この役割を担うのがSOCです。
SOCは、エンドポイントのみならずネットワークやクラウド環境を含めた広範囲での監視を実施し、異常を検知した際には、迅速かつ的確にインシデント対応を行います。SOCとの連携によってEDRで検出されたアラートの重要度を判断し、サイバー攻撃の全体像を把握した上で迅速に対応し、被害を封じ込めることができます。
また、SOCを活用することで、人員が限られる中小企業でも、高度なセキュリティ体制の構築が可能です。EPPとEDRの連携に加えてSOCを統合することで、実用的で現場に即したセキュリティ体制を構築し、重大なセキュリティインシデントの予防と影響の最小化につながるでしょう。
SOCについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
「EDRのアラートが多すぎて対応しきれない」「セキュリティ人材が不足していてSOCまで手が回らない」といったお悩みはありませんか?SOCサービス「セキュリモ」は、24時間365日の監視体制と専門アナリストによる迅速な対応により、EPP・EDRの力を最大限に引き出し、貴社のセキュリティ運用を強力に支援します。インシデント対応の負担軽減や組織全体のセキュリティ強化をお考えなら、ぜひ「セキュリモ」の導入をご検討ください。
EPPの導入メリット
EPPは、サイバー攻撃から企業のエンドポイントを守るだけでなく、業務効率の向上やコスト削減など経営面でも多くのメリットがあります。ここでは、以下の2つの視点からEPP導入によるメリットを解説します。
- コスト削減と効率化
- セキュリティの強化とリスクの最小化
コスト削減と効率化
EPPの導入メリットの1つは、コスト削減と効率化です。
EPPの導入により、企業は複数のセキュリティ製品を個別に管理・運用する負担を軽減できます。EPPは、ウイルス対策、ファイアウォール、侵入防止、デバイス制御などの機能を一元的に搭載しているため、ライセンスコストや運用工数を大幅に抑制できます。
また、EPPにはクラウド型の製品も多く、拠点ごとに分散した端末の状況を一元管理可能です。これにより、セキュリティパッチの適用状況や脅威検知の有無をリアルタイムで把握でき、従来の手動・個別対応にかかる手間を削減できます。
これらの効率化により、IT部門の人的リソースを戦略的な業務に振り分けることが可能となり、結果として、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。
セキュリティの強化とリスクの最小化
セキュリティの強化とリスクの最小化も、EPPの導入メリットです。
EPPは、多層的なセキュリティ機能を統合して提供することで、企業全体のセキュリティ水準を向上させます。ウイルスやマルウェアのリアルタイム検知・防止はもちろん、ネットワーク、端末の異常挙動に対する対応力も強化され、情報漏洩・システム停止といった重大リスクの予防と影響の軽減に役立ちます。
さらに、EPPはEDRや次世代アンチウイルス、SOCと連携させることで、予防から検知、対応、復旧までを一貫してカバーする包括的なセキュリティ体制の構築が可能です。これにより、サイバー攻撃の被害を最小限に抑え、コンプライアンス上のリスクの低減にも役立ちます。例えば、個人情報保護法や業界ごとのセキュリティ基準への違反による行政処分、訴訟リスクを未然に防ぐことができます。
EPPの導入は、単なるIT対策ではなく、企業の事業継続性や信頼性を支える戦略的な投資といえるでしょう。
EPPを活用して、安全なIT環境を構築しよう
EPPは、従来のウイルス対策を超えて企業のエンドポイントを多層的かつ包括的に保護する高度なセキュリティソリューションです。
サイバー攻撃の手法がますます巧妙化・高度化する中で、エンドポイントは企業の脆弱性が集中する侵入経路として狙われやすくなっています。EPPを導入することで、こうしたリスクに対し、「予防」「検知」「対応」のすべてのフェーズを包括的にカバーします。
また、EPPはEDRとの連携によって事後対応の精度と処理速度を向上させ、SOCとの併用により、24時間体制でのセキュリティ監視と対応が可能です。さらに、次世代アンチウイルスなどの先進技術を組み合わせることで、未知の脅威にも柔軟に対応できます。こうした多層的な防御体制の構築は、IT部門の負担軽減にとどまらず、企業全体のリスク管理体制の強化にもつながります。常に変化する脅威に対応するには、最新の技術を取り入れたEPPの導入と継続的な運用が重要です。
安全なIT環境を実現するために、EPPを中心とした包括的なセキュリティ体制の構築を本格的に検討してみてはいかがでしょうか。
SOCサービス「セキュリモ」なら、専門アナリストが24時間365日体制で監視・分析・対応を代行し、EPPやEDRの導入効果を最大限に引き出します。自社のリソースに不安がある場合でも、セキュリティの強化と運用負荷の軽減を両立できます。EPPの導入とあわせて、「セキュリモ」の活用もぜひご検討ください。



