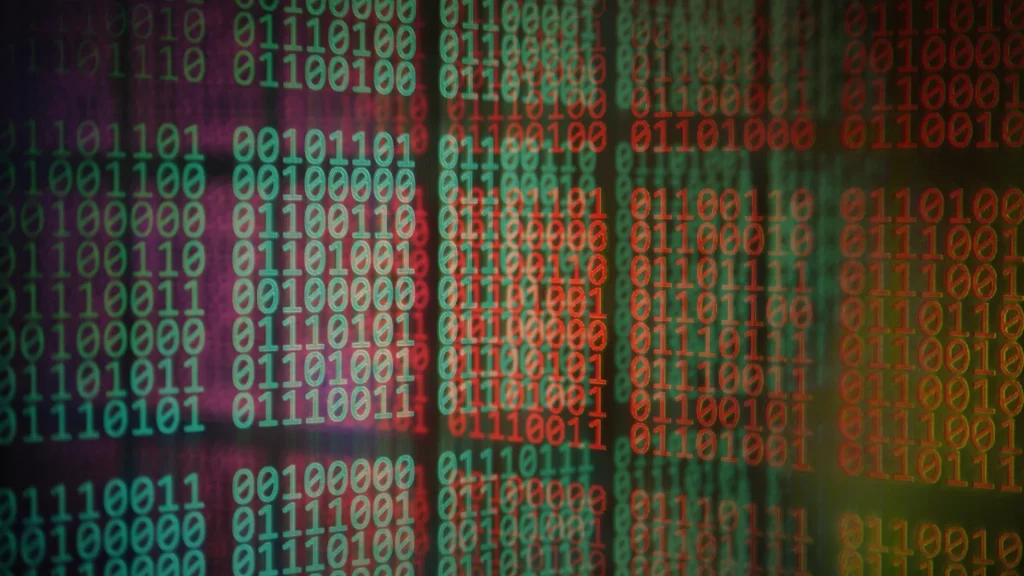サイバーセキュリティを語るうえで、マルウェアの脅威は決して見逃せません。そのなかでも近年注目を集めているのが「Mirai」です。IoT機器を標的とするこのマルウェアは、家庭用から産業用まで幅広い機器に感染し、大規模なDDoS攻撃などを引き起こす原因となっています。ネットワークカメラやルーターなど、一見セキュリティリスクが小さいと思われがちなIoT機器を足がかりとして、企業や社会インフラに深刻な被害をもたらすのです。
この記事では、Miraiがどのように誕生したのか、どのような仕組みで感染を拡大していくのか、そして実際にどのようなリスクが生じるかについて解説します。さらに、企業や組織の情報システム部門が取るべき対策や、防御のポイントもあわせて紹介しますので、IoT機器を用いた業務環境やサービスを安全に維持するための参考にしていただければ幸いです。
Mirai(マルウェア)
Miraiは2016年ごろに初めて大きく報道されたマルウェアとして知られています。その大きな特徴は、これまでパソコンやサーバーを狙う攻撃が主流だったところを、ネットワークカメラやルーターなどのIoT機器に狙いを定めた点にあります。IoT機器は近年、家庭だけでなく産業や企業の現場にも広く導入されるようになりましたが、初期設定のまま使われているケースや、セキュリティアップデートの頻度が低いケースが少なくありません。
Miraiの開発者たちは、こうしたIoT機器の“セキュリティホール”に目をつけたのです。リソースの限られた小型機器は、パソコン向けの強固なセキュリティソフトを導入しにくいこともあり、狙われやすいターゲットでした。Miraiが広く知られるきっかけとなったのは、IoT機器を大量に感染させ、膨大なネットワークトラフィックを一斉に送りつけるDDoS攻撃が成功し、ネットサービスの一部が大規模ダウンした事件です。この一件で、IoT機器のセキュリティを見直す必要があるとの意識が、企業や一般ユーザーの間でも高まったのではないでしょうか。
Miraiの仕組みと感染経路
Miraiの仕組みを理解するうえで重要なのは、攻撃者が脆弱なパスワードを狙うという点です。具体的には、工場出荷時のデフォルトパスワードや、推測しやすい文字列を総当たりで試すブルートフォース攻撃を行い、認証を突破したのちにIoT機器の内部に潜り込みます。パスワードの強度が低い機器ほどあっという間に制御権を奪われ、Miraiのボットネット網に組み込まれてしまいます。
一度感染に成功すると、Miraiはその機器から周辺のネットワークをスキャンし、同様の脆弱なデバイスを探して感染を拡大していきます。企業のネットワーク内に入り込んだ場合、セキュリティレベルの低い端末や未使用のポートを通じて被害が連鎖的に広がる可能性があります。このように、Miraiはデフォルト設定のまま放置されているIoT機器や更新の行われない機器を足がかりに、短時間で大規模なボットネットを形成できるのです。
Mirai(マルウェア)のリスクと脅威
DDoS攻撃の大規模化
Miraiがもたらす最大の脅威のひとつが、DDoS攻撃の大規模化です。従来のDDoS攻撃でも、インターネットに接続された無数のコンピューターを踏み台にする「ボットネット」は存在しましたが、MiraiはIoT機器という新しい踏み台を得ることで、そのパワーをさらに拡大させています。
ネットワークカメラやルーターなどは24時間常時稼働していることが多く、攻撃者にとっては“使い勝手”の良い兵力に変貌します。あるとき攻撃者が命令を出せば、感染した数万台、数十万台のデバイスが一斉に標的サーバーへリクエストを送りつけ、サービスをダウンさせる可能性があります。これによって企業やサービスプロバイダのサイトが閲覧不能になるだけでなく、通信インフラの一部にまで影響が及ぶことも懸念されます。
IoT機器への深刻な影響
企業の情報システム部門の観点からは、社内ネットワークに接続されているIoT機器がMiraiに感染することで、思わぬ形で業務に支障をきたすリスクが高まります。例えば、防犯カメラや会議システムなど一見無害に思える端末を足がかりとして、他のシステムやデータベースにまで侵入経路を拡張されてしまうかもしれません。
また、重要な制御システムとIoT機器が同じネットワーク内に存在している場合、サイバー攻撃者は産業用機器やインフラ管理システムにも手を伸ばすチャンスを得ます。万が一、社会インフラに影響するような攻撃が成功すれば、企業としては責任問題にも発展するおそれがあります。こうした深刻なリスクを未然に防ぐためにも、IoT機器のセキュリティ対策は慎重に行う必要があるのです。
Mirai(マルウェア)対策
🟢IoT機器のパスワード・設定強化
Miraiの感染経路を断ち切るうえで、まずはIoT機器の初期パスワードを必ず変更することが重要です。安易なパスワードや工場出荷時のままの設定は、攻撃者にとって侵入しやすい“扉”を開け放しているようなものです。さらに、不要な機能やサービスが動いている場合はそれらを無効にし、管理画面へのアクセスが社内ネットワークからだけに限定されるような設定も検討すべきでしょう。
このように、自分たちのIoT機器がどのような機能を持ち、どういったポートが開かれているのかを把握することが、Miraiによる被害を防ぐ第一歩となります。企業の情報システム部門にとっては、すべてのIoT機器を一覧にまとめ、セキュリティポリシーに沿ったパスワード管理やアクセス制御を徹底することが欠かせません。
🟢ファームウェアアップデートと脆弱性管理
IoT機器のメーカーから定期的に提供されるファームウェアアップデートは、セキュリティ上の脆弱性を修正する重要な手段です。特に、Miraiのようにブルートフォース攻撃以外の脆弱性も悪用してくるマルウェアの場合、最新のアップデートを適用していない機器は格好の標的になります。
さらに、製品によってはメーカーのサポート期間が終了しているケースもあるため、そうした機器をそのまま使い続けると、更新のない脆弱性を永久に抱えるリスクを背負うことになります。企業としては、使用しているIoT機器のライフサイクルやサポート状況を管理し、必要に応じて更新や交換を検討することが望ましいでしょう。
🟢ネットワーク分離と監視体制
IoT機器のセキュリティを高めるうえでは、ネットワーク構成の見直しも有効な手段です。重要なサーバーやデータベースとIoT機器が同一ネットワークに混在している場合、たとえ一台のIoT機器がMiraiに感染しただけで、全社的に被害が拡大するリスクが高まります。ネットワーク分離によってIoT機器用のセグメントを設け、万が一感染が発生しても被害を最小限に抑えられるようにしておくと安心です。
あわせて、ログ監視や異常通信をチェックする仕組みを導入することで、Miraiが通信を行いはじめた段階で迅速に異常を検知できます。監視体制を整え、日頃から不審な動きがないかを定期的にチェックすることで、サイバー攻撃に素早く対処し、被害を拡散させない対策が可能になるでしょう。
Mirai(マルウェア)は、IoT機器のパスワードや設定の甘さを突いて感染を広げ、大規模なDDoS攻撃やネットワーク侵入を引き起こす厄介な脅威です。特に、IoT機器はセキュリティ対策がおろそかになりがちであり、企業の情報システム部門にとっては従来のPCやサーバーとは違った観点からの対策を練る必要があります。
まずはデフォルトパスワードの変更やファームウェアアップデートの実施など、基本的な守りを徹底することがMirai対策の第一歩といえるでしょう。さらに、ネットワーク分離やログ監視などの多層的な防御策を講じることで、万が一の感染拡大を抑えられる仕組みを整えることが重要です。IoT機器の活用が進むにつれ、Miraiのような新種・亜種のマルウェアもますます進化していくことが予想されます。常に最新の情報を収集しながら、適切な対策を講じることで、企業のサービスや業務を堅実に守っていきましょう。
サイバー攻撃対策をするなら
✅未知の攻撃にも対応できるセキュリティツールの導入
サイバー攻撃に対処するためには、最新のセキュリティツールの導入が不可欠です。特に、ランサムウェアやゼロデイ攻撃に対しては、従来のウイルス対策ソフトでは不十分であり、AIを活用したEDR(Endpoint Detection and Response)や次世代ファイアウォールの導入が効果的です。これらのツールは、未知の脅威にも迅速に対応でき、攻撃が発生する前にシステムを保護することが可能です。
✅セキュリティについて従業員教育を行う
サイバー攻撃対策を効果的に実行するためには、技術的なツールの導入だけでなく、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることも重要です。多くのサイバー攻撃は、従業員の不注意や不正な操作によって引き起こされるケースが少なくありません。特に、フィッシングメールや悪意のあるリンクをクリックしてしまうことによる情報漏えいは防止可能なものです。定期的なセキュリティ研修やシミュレーションを行うことで、従業員が最新の攻撃手法を理解し、適切な対応を取れるようになります。
✅セキュリティ対策のガイドラインを策定する
効果的なセキュリティ対策を実施するためには、企業ごとに具体的なセキュリティガイドラインを策定することが求められます。このガイドラインでは、データの取扱い方法、アクセス権の設定、アプリケーションの使用制限など、業務に関連するセキュリティポリシーを明確に定義します。従業員が守るべきセキュリティ基準を文書化することで、全員が一貫したセキュリティ対策を実施できる環境を構築します。
また、ガイドラインを定期的に見直し、最新のサイバー攻撃手法に対応するために必要な変更を加えることも重要です。企業の業務内容や使用する技術の変化に応じて、適切にセキュリティポリシーを更新することで、サイバー攻撃に対する防御力を維持できます。
アクトはSentinelOneとMSSP契約を持つ正式パートナーとして、 平常時からインシデント対応までお客さま負担をかけることなく、最高レベルのサイバーセキュリティをご提供します。