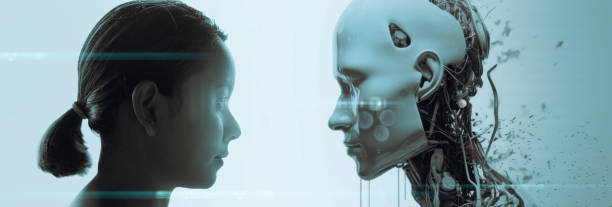独立行政法人情報処理推進機構(IPA、理事長:齊藤裕)は2025年8月29日、国内企業の営業秘密管理の実態を調査した「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」の報告書を公開した。
調査では、過去5年以内に営業秘密の流出を認識した企業の割合が 35.5% に上り、2020年調査時の 5.2% から急増していることが明らかになっている。
技術情報や顧客データなど、企業競争力の源泉となる営業秘密の管理が、これまで以上に重要な課題とされている。
流出ルートと流出先の多様化
流出原因として最も多かったのは「外部からのサイバー攻撃」(36.6%)で、前回の8.0%から大幅に増加。
さらに、「現職従業員のルール不徹底」(32.6%)や「金銭目的による内部不正」(31.5%)も上位に入り、内部要因によるリスクの高さが挙げられている。
流出先は「国内の競合他社」が54.2%と最多だった、「国内の競合他社以外の企業」も48.8%と急増しており、取引先や外部組織を経由した流出の広がりが懸念されている。
新技術の普及と管理上の課題
企業のIT環境にも大きな変化が見られているとのことで、クラウドサービスを業務で利用している割合は50.4%と、2020年調査の22.6%から倍以上に増加。
また、生成AI(Generative AI、文章や画像を自動生成する人工知能)の業務導入については、52.0%の企業が何らかのルールを設けていたが、「利用を許可する」企業が25.8%、「利用を禁止する」企業が26.2%と、対応は二分しているとのこと。
IPAは「適切なルール作りと安全な活用が今後の競争力強化の鍵になる」と指摘している。
さらに、従業員が退職後に競合企業へ転職することを制限する「競業避止義務契約」の締結率も上昇傾向にある一方で、違反の発見が難しいという課題も浮上。
営業秘密管理の難易度は高まり続けている。
経営層と現場の認識にギャップ
調査では、経営層と現場担当者の間で営業秘密流出リスクに対する認識の差があることも確認されており、IPAは「サイバー攻撃と内部不正の両面での対策強化に加え、組織全体での意識統一が急務」と強調する。
また、企業が本調査結果を参考に営業秘密の管理体制を見直し、流出防止策を強化することを強く呼びかけており、特に中小企業においてはリソース不足から対策が後手に回る傾向があり、リスクが高まっていると警鐘を鳴らしている。