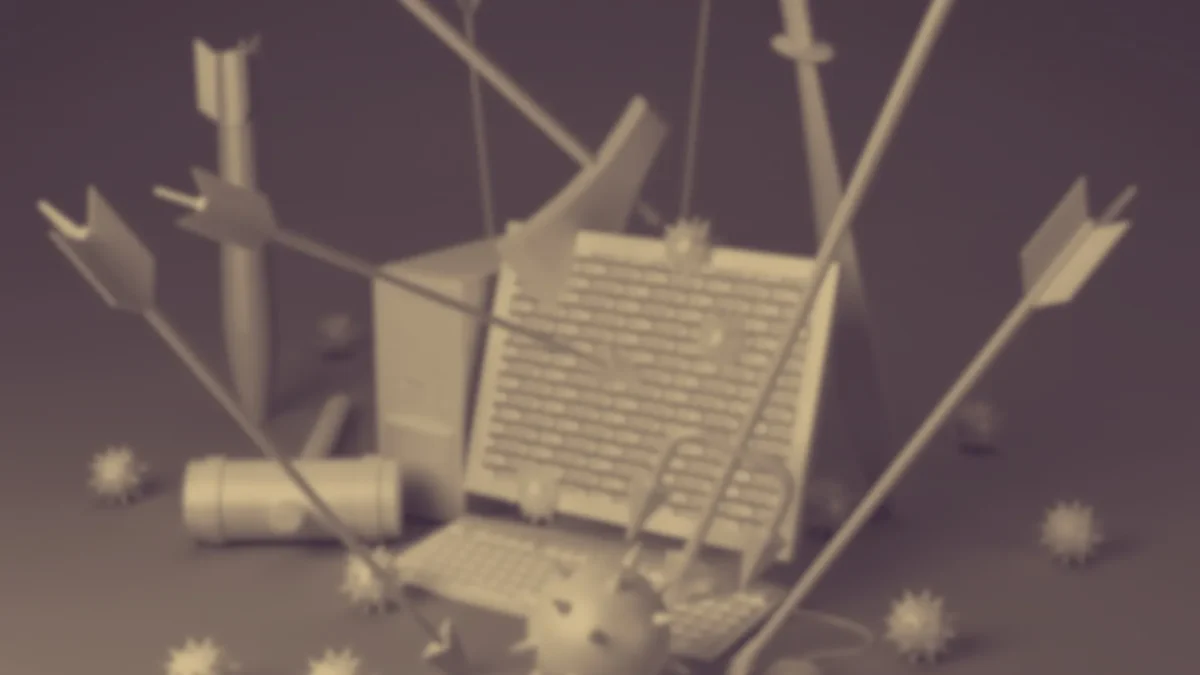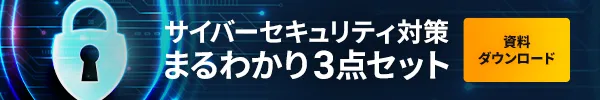サイバー攻撃の脅威は年々増大しており、企業の情報システム部門が担うべき役割もますます大きくなっています。攻撃者はあらゆる手段を駆使してデータを盗み出したり、サービスを停止に追い込んだりするため、単一のセキュリティ対策のみでは十分とはいえません。そこで本記事では、サイバー攻撃の概要と、企業が特に注意すべき代表的な手口を幅広く紹介し、そのリスクや対策について解説します。サイバー攻撃を体系的に理解し、実際にどのような防御策を講じるべきかを考える上での参考にしていただければ幸いです。
サイバー攻撃とは
サイバー攻撃とは、インターネットや企業内ネットワークを介してシステムやデータに不正アクセスしたり、情報を盗み出したりする行為を指します。IT化が進む現代では、企業活動の大部分がコンピューターやネットワークに依存しており、それらが攻撃を受けると業務停止や情報漏えいなど深刻な被害が生じる可能性があります。攻撃者もまた高度な技術を習得し、専用ツールや不正なサービスを利用しながら攻撃手法を進化させており、企業側は絶えず新たな対策を考え続ける必要があります。
企業が直面する脅威の現状
企業にとってサイバー攻撃は、単純なシステムダウンだけでなく、信頼失墜や金銭的損失など多方面にわたる深刻な影響をもたらします。特に、情報システム部門が担うべき業務範囲が拡大するとともに、クラウドやモバイル端末、IoT機器など守るべき領域も増加しており、従来のセキュリティ対策のみでは追いつかない事態が発生しがちです。攻撃手法もフィッシングやランサムウェアをはじめ、さまざまなパターンで巧妙化しているため、それぞれの特徴を把握して対策を講じることが不可欠です。
サイバー攻撃の手口一覧
🔴フィッシング攻撃
フィッシング攻撃は、企業やサービスの公式サイトを装ったメールやメッセージを送付し、受信者に個人情報やログイン情報を入力させる手法です。偽装されたログインページや偽の警告を見せることで、ユーザーに慌てさせ、本来は知られてはならない認証情報を攻撃者に渡してしまう結果につながります。ここで得られた情報をもとに、マルウェアを拡散したり、企業ネットワークに侵入してさらなる攻撃を仕掛けるケースも少なくありません。
📚関連記事:フィッシング詐欺とは?概要と手口、対策をわかりやすく解説!
🔴ランサムウェア攻撃
ファイルを暗号化し、身代金の支払いと引き換えにデータを復旧させることを目的とするのがランサムウェア攻撃です。近年ではDouble Extortion(恐喝型)と呼ばれる手法が普及しており、暗号化したデータを人質にとるだけでなく、機密情報を外部に公開するという二重三重の脅迫を行うパターンが増えています。攻撃を受けると業務が停止し、大きな復旧コストや信頼失墜を招く恐れがあります。
📚関連記事:ランサムウェアによる業務停止事例とEDRの役割を解説
🔴DDoS攻撃(分散型サービス妨害)
複数の端末を用いて標的となるサーバーやネットワークに膨大なトラフィックを送り込み、サービスを一時的または長期的に停止させるのがDDoS攻撃です。攻撃者がボットネットを形成して大規模なトラフィックを発生させる場合、クラウド事業者や大手ウェブサイトであっても対処が難しくなるほど深刻化しています。サービス停止は顧客離れや売上減少など直接的なビジネスインパクトをもたらします。
📚関連記事:DDoS攻撃で実際に起きた被害事例と対策をわかりやすく解説!
🔴SQLインジェクション
Webアプリケーションの入力フォームやURLパラメータに不正なSQL文を挿入し、データベースから情報を盗み出したり改ざんしたりするのがSQLインジェクションです。脆弱なアプリケーションではユーザーの入力内容が適切にエスケープ処理されないため、攻撃者は自由にデータベースへ命令を送り込めるようになります。基本的な脆弱性対策がなされていないシステムは狙われやすく、大規模漏えい事件の原因となることも珍しくありません。
📚関連記事:SQLインジェクションとは?概要と被害事例、対策を解説
🔴クロスサイトスクリプティング(XSS)
Webサイトに悪意あるスクリプトを埋め込み、アクセスしたユーザーのブラウザで不正な処理を実行させる手口がクロスサイトスクリプティング(XSS)です。これにより、ユーザーのセッション情報を奪ったり、フィッシングサイトへ自動的にリダイレクトさせたりと、さまざまな悪用が可能になります。対策としては入力値のエスケープや出力時のサニタイズが有効ですが、複数のページやパラメータを対象に徹底する必要があるため、実装ミスが起きやすいのも事実です。
📚関連記事:クロスサイトスクリプティング(XSS)とは?概要から対策まで解説
🔴中間者攻撃(MITM)
ユーザーとサーバーの通信経路の途中に攻撃者が割り込み、通信内容を盗み見たり改ざんしたりするのが中間者攻撃です。暗号化されていない通信や、不正なWi-Fiスポットなどを経由すると発生しやすくなり、認証情報やクレジットカード情報が流出する原因となります。HTTPSやVPNの利用によりリスクを低減できますが、ルート証明書の不正取得など手の込んだ手口も存在するため、一筋縄ではいきません。
📚関連記事:中間者攻撃(MiTM攻撃)とは?概要や仕組み、リスクを解説!
🔴水飲み場攻撃
特定の組織や業界のユーザーが頻繁に訪れるWebサイトをあらかじめ改ざんし、そこにアクセスした被害者をマルウェアに感染させる手法を水飲み場攻撃と呼びます。不特定多数を狙う攻撃とは異なり、比較的限定されたターゲット層を狙いつつ、確実に被害を広げる狙いがあります。企業や公共機関の内部ネットワークへ潜入する入り口として利用されることも多く、発見が遅れると深刻な情報漏えいに発展するリスクがあります。
📚関連記事:水飲み場型攻撃とは?手口や想定されるリスク、対策をわかりやすく解説
🔴ゼロデイ攻撃
ソフトウェアやOSに存在する脆弱性が、開発元でも把握されていない状態で悪用される手口がゼロデイ攻撃です。脆弱性が判明してからパッチが提供されるまでの間に攻撃が実行されるため、伝統的なセキュリティ対策では防ぎきれないケースがあります。攻撃者に先手を取られると多くのシステムが同時に危険にさらされる可能性があるため、高度な脅威インテリジェンスの活用や監視体制の強化が求められます。
📚関連記事:ゼロデイ攻撃の事例とは?被害にあった場合の対応と対策を解説!
🔴サプライチェーン攻撃
企業と取引関係にあるベンダーや協力会社のシステムを狙い、そこを踏み台にして最終的な標的企業に侵入するのがサプライチェーン攻撃です。セキュリティ体制が比較的手薄なサプライヤーを経由するため、メインターゲットへの防御をかいくぐれる可能性が高まります。大手企業や公共機関もこうした形で内部への侵入を許してしまった事例が報告されており、サプライヤー管理の厳格化が喫緊の課題となっています。
📚関連記事:標的は中小企業?増加しているサプライチェーン攻撃とは?
🔴パスワードクラック攻撃
パスワードクラック攻撃は、ブルートフォース攻撃や辞書攻撃を用いてユーザーのパスワードを破り、システムへの不正アクセスを試みる手口です。脆弱なパスワードや使い回しが横行している場合、攻撃成功率が飛躍的に高まります。攻撃者は大量のアカウント情報を流出データから入手し、総当たりでログインを試すことで企業システムに潜入する可能性を探ります。
📚関連記事:ブルートフォース攻撃とは? 概要と対策を解説
🔴ドライブバイダウンロード攻撃
悪意のあるWebページにアクセスしただけでマルウェアが自動的にダウンロード・実行されるのがドライブバイダウンロード攻撃です。ブラウザやプラグインに存在する脆弱性を狙うことが多く、ユーザーの操作なしで感染が成立するため非常に危険です。OSやブラウザのバージョンが古い環境では、効果的な防御手段がなく、セキュリティソフトにも気づかれにくい場合があります。
📚関連記事:ドライブバイダウンロード攻撃とは?仕組みやリスク、対策を解説!
🔴標的型攻撃(APT)
特定の企業や組織を狙い、長期間にわたって潜伏しながら機密情報を収集するのが標的型攻撃(APT)です。侵入経路はフィッシングメールやゼロデイ脆弱性など多岐にわたり、攻撃者は段階的にネットワーク内の権限を高めながら最終的に重要サーバーや機密データに到達します。一度内部に入り込まれると検知が難しく、気づいたときには大規模な情報漏えいが起きている恐れがあります。
📚関連記事:標的型攻撃の被害事例とは?概要から対策までわかりやすく解説!
サイバー攻撃がもたらすリスクと影響
情報漏えいと金銭的損失
サイバー攻撃が成功すると、顧客データや取引情報などの機密情報が外部に流出し、企業は信頼失墜や損害賠償の負担を強いられる可能性があります。ランサムウェアによる暗号化を解除するために身代金の支払いを余儀なくされるケースや、復旧にかかる作業費用が膨大になるケースもあり、財務的にも大きな打撃を受けるリスクが高まります。
事業停止と社会的信用の喪失
サイバー攻撃によってネットワークや基幹システムが停止し、業務が継続できなくなる事態は非常に深刻です。サービスの停止が長引けば、それだけ顧客や取引先との信頼関係に傷がつき、今後のビジネスにも影響を与えかねません。また、社会的な批判や株価の下落など、企業のイメージや評価にも直接影響するため、被害を最小限に食い止めるための早期対応とリカバリ計画が求められます。
サイバー攻撃への主な対策
🟢多層防御の構築
サイバー攻撃は多方面から仕掛けられるため、ファイアウォールやウイルス対策ソフトだけでは不十分です。侵入を防ぐだけでなく、侵入後の動きを監視・遮断するIDS/IPSやEDRの活用が効果的です。加えて、ネットワークを複数のセグメントに分割し、不要な通信を制限するなど、多層的な防御策を組み合わせることで、万が一の侵入後も被害が拡大しにくい環境を作ることができます。
🟢セキュリティ意識の向上と教育
多くの攻撃は従業員のヒューマンエラーを起点に成功するため、フィッシングメールへの対処法やパスワード管理の重要性を社内で共有することが欠かせません。定期的にセキュリティ研修を行い、具体的な事例を示しながら従業員のリテラシーを高めることが、被害を防ぐうえで大きな効果を発揮します。
🟢システム・ソフトウェアの最新化
脆弱性を放置していると、攻撃者にとって絶好の狙いどころとなります。OSやアプリケーション、プラグインなどを常に最新バージョンに保ち、不要なソフトウェアはアンインストールすることで、攻撃の足がかりを減らすことができます。特にゼロデイ攻撃を想定する場合、製品メーカーやセキュリティベンダーからの緊急パッチ情報にはこまめにアンテナを張ることが重要です。
🟢インシデント対応計画と監視体制
サイバー攻撃は完全には防げない前提で、被害を最小限に抑える体制づくりも大切です。セキュリティオペレーションセンター(SOC)を活用し、リアルタイムでのログ分析やアラート確認を行うことで、不審な挙動を早期に発見できます。インシデントが発生した際には、迅速な封じ込めと復旧が求められるため、具体的な対応手順を明文化しておき、定期的にシミュレーションを行うことが効果的です。
さいごに
サイバー攻撃の手口は多岐にわたり、フィッシングやランサムウェア、DDoSといった耳慣れたものから、ゼロデイ攻撃やサプライチェーン攻撃のように発見が遅れやすい高度な手法まで、企業は常に広範なリスクにさらされています。こうした攻撃の存在を理解せずに単一の対策だけを導入しても、スキを突かれれば大きな損害を被る恐れがあります。
ファイアウォールやウイルス対策ソフトだけでなく、ネットワーク分割やIDS/IPS、EDRなど多層的な防御を講じ、従業員のセキュリティ意識を高めることが重要です。さらに、OSやアプリケーションを最新状態に保ち、インシデントが起きた場合の対応計画と監視体制を整えておくことで、被害を最小限に抑え、迅速に復旧することが可能になります。サイバー攻撃は今後も変化と発展を続けるため、企業の情報システム部門としては継続的に最新動向を把握し、柔軟かつ強固なセキュリティ対策を構築していくことが不可欠です。
サイバー攻撃対策をするなら
✅未知の攻撃にも対応できるセキュリティツールの導入
サイバー攻撃に対処するためには、最新のセキュリティツールの導入が不可欠です。特に、ランサムウェアやゼロデイ攻撃に対しては、従来のウイルス対策ソフトでは不十分であり、AIを活用したEDR(Endpoint Detection and Response)や次世代ファイアウォールの導入が効果的です。これらのツールは、未知の脅威にも迅速に対応でき、攻撃が発生する前にシステムを保護することが可能です。
✅セキュリティについて従業員教育を行う
サイバー攻撃対策を効果的に実行するためには、技術的なツールの導入だけでなく、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることも重要です。多くのサイバー攻撃は、従業員の不注意や不正な操作によって引き起こされるケースが少なくありません。特に、フィッシングメールや悪意のあるリンクをクリックしてしまうことによる情報漏えいは防止可能なものです。定期的なセキュリティ研修やシミュレーションを行うことで、従業員が最新の攻撃手法を理解し、適切な対応を取れるようになります。
✅セキュリティ対策のガイドラインを策定する
効果的なセキュリティ対策を実施するためには、企業ごとに具体的なセキュリティガイドラインを策定することが求められます。このガイドラインでは、データの取扱い方法、アクセス権の設定、アプリケーションの使用制限など、業務に関連するセキュリティポリシーを明確に定義します。従業員が守るべきセキュリティ基準を文書化することで、全員が一貫したセキュリティ対策を実施できる環境を構築します。
また、ガイドラインを定期的に見直し、最新のサイバー攻撃手法に対応するために必要な変更を加えることも重要です。企業の業務内容や使用する技術の変化に応じて、適切にセキュリティポリシーを更新することで、サイバー攻撃に対する防御力を維持できます。
アクトのサイバーセキュリティ対策支援
アクトはSentinelOneとMSSP契約を持つ正式パートナーかつ、国内唯一のIRパートナーであり、 平常時からインシデント対応までお客さま負担をかけることなく、最高レベルのサイバーセキュリティをご提供します。また、IT導入補助金を活用して導入することも可能です。
ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。