ゼロトラストとはなにかをわかりやすく解説|基本の考え方・具体例・導入メリットと課題
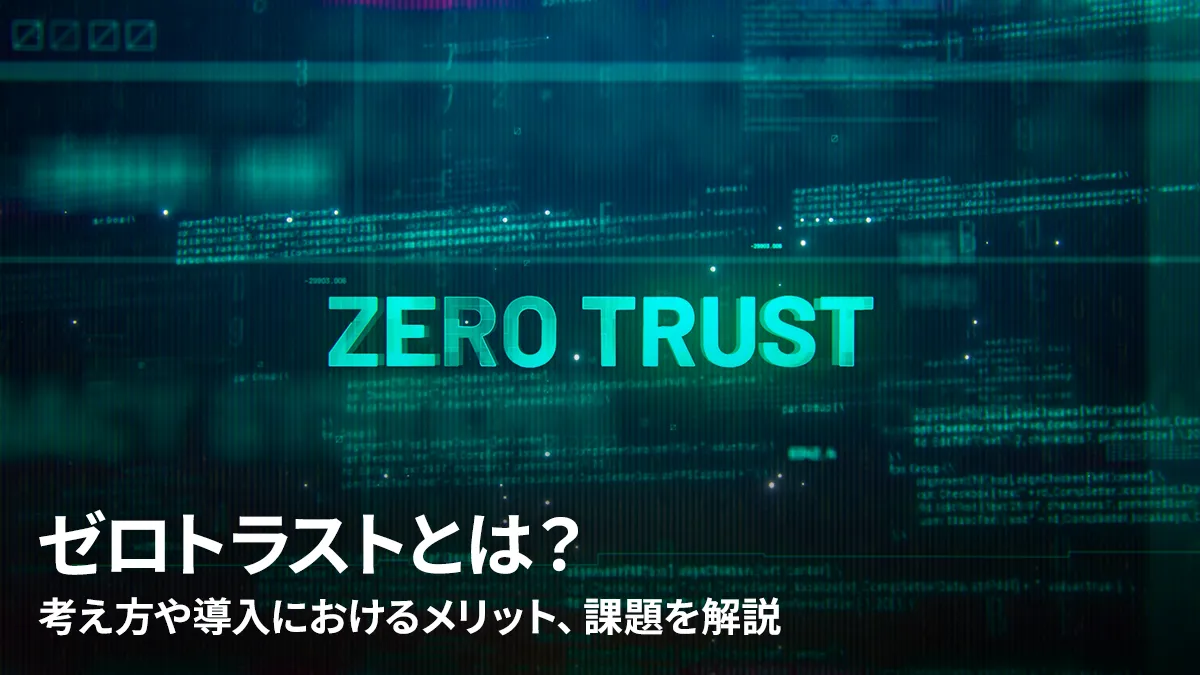
サイバー攻撃の巧妙化やクラウド活用の進展により、企業のセキュリティ体制は大きな転換点に差し掛かっています。そのような中、注目されているのが「ゼロトラスト」というセキュリティモデルです。ゼロトラストは「すべてのアクセスを信頼しない」ことを前提とし、ユーザーやデバイスの状態を常時検証・認証することで、安全なIT環境を維持します。従来の境界型防御と異なり、社内外を問わずすべての通信・アクセスを検証対象とする点が大きな特徴です。
本記事では、ゼロトラストの基本的な考え方や導入によるメリット、課題、構成要素を解説します。
目次
「境界のないクラウド環境でも安全に業務を行いたい」「社内外からのアクセスを制御したい」そのような課題を抱える企業が今、注目しているのがゼロトラストという考え方です。ID・デバイス・アクセスの一元管理は、ゼロトラストに向けた第一歩となります。まずは、「JumpCloud」の導入から、安全な認証と管理の仕組みを整えてみてはいかがでしょうか。
ゼロトラストとは、ネットワークの内外を問わず「すべてのアクセスを信頼しない」セキュリティモデル
ゼロトラストとは、「すべてのアクセスを信頼しない」ことを前提にしたセキュリティモデルです。従来のように社内ネットワークを安全と見なす「境界型防御」は、は、オフィス内のネットワークに限ってセキュリティを構築する考え方でした。しかし、クラウドサービスの活用や社外からのリモートアクセスが一般化した現在では、社内外の明確な境界がなくなりつつあり、境界型防御では外部からのアクセス、内部不正に十分対応できません。ゼロトラストでは、ユーザーや端末の場所を問わず、アクセスのたびに認証・検証を行い、必要最小限の権限で利用を許可します。これにより、内部からの脅威や情報漏洩のリスクを低減しやすくなります。
ゼロトラストを導入するためには、さまざまなセキュリティ技術を組み合わせる必要があります。主な対策は以下のとおりです。
ゼロトラストを導入するための主な対策
- ユーザーの本人確認(ID・パスワードに加えて複数の要素を使った認証のMFA(多要素認証)を使用)
- 端末の状態チェック(セキュリティソフトの有無やOSのアップデート状況など)
- 通信の暗号化(VPNやSSLによる保護)
- リアルタイムのログ監視と異常検知
- アクセス権限の最小化と動的制御
これらの施策を統合的に運用することで、ゼロトラストにより強固なセキュリティ体制の構築が可能となります。ただし、すべてを一度に取り入れる必要はありません。むしろ、自社にとっての優先事項を見極め、どこから取り組むかを考えることが、導入成功への第一歩となるでしょう。
ゼロトラストが必要とされる背景
近年、従来の境界型防御では対処が難しい新たなリスクが顕在化し、より柔軟かつ堅牢なセキュリティ体制が求められるようになりました。ここでは、ゼロトラストが必要とされる背景について解説します。
リモートワークの普及とセキュリティリスク
リモートワークの普及により、従業員が自宅や外出先から社内システムにアクセスする機会が大きく増えています。これに伴い、従来のように社内ネットワークを前提としたセキュリティ対策では対応しきれず、アカウントの不正利用、私物端末からのマルウェア感染など多様なリスクにさらされるようになっています。VPNによる暗号化は、外部ネットワークとのやり取りを保護する点では有効です。しかし、VPNだけではアクセス後のユーザーの操作内容や端末の安全性までは保証できず、マルウェア感染や内部不正などのリスクは残ります。
ゼロトラストは、アクセスのたびにユーザーや端末を検証し、信頼できると判断された場合のみアクセスを許可します。これにより、リモート環境でも高いセキュリティを保つことが可能です。
クラウドサービスの利用増加
クラウドサービスの利用増加も、ゼロトラストが必要とされる背景の1つです。
近年では、データやシステムが従来のように社内サーバー上ではなく、クラウド上に存在することが一般的になっています。この状況では、社内ネットワークの内側を安全と見なして通信を制限する従来の防御策では、クラウド上の情報を十分に守ることができません。
ゼロトラストでは、クラウド上でもすべてのアクセスを検証対象とし、ユーザーや端末の状況に応じてアクセス権限を細かく制御します。これにより、クラウド環境でも安全な利用が可能になります。ただし、ゼロトラストの導入にあたっては、既存のネットワークや業務システムとどう連携させるかを事前に検討して、必要に応じて調整することが重要です。
ゼロトラストを理解するための基本的な考え方
ゼロトラストは、社内だから安全という前提を置かず、すべてのアクセスをそのつど確認し続ける考え方です。一度ログインしたから安心と捉えるのではなく、常に「本当に安全か」を確かめながら利用を許可する仕組みだと理解すると分かりやすいでしょう。従来の社内ネットワークは、一度受付を通れば社内のフロアを自由に移動できるオフィスに近い考え方でした。それに対してゼロトラストは、フロアごとにカードキーで確認しながら進むオフィスのように、利用のたびに正当性を確かめるイメージです。
ここでは、ゼロトラストの根幹となる2つの考え方をわかりやすく整理します。
常に確認する重要性
ゼロトラストの中核となる考え方の1つが、「常に確認する重要性」です。
ゼロトラストでは、アクセスのたびにユーザーや端末の状態を確認します。一度認証された後も常に検証を繰り返すことで、ID・パスワードの漏洩による不正アクセスを防ぐことが可能です。異常が検知された場合には即座に遮断または制限を行います。
この継続的な検証を行うことで、不正アクセスの早期発見や内部脅威への対処も可能です。「一度許可したら信頼する」のではなく、「常に確認する重要性」が、ゼロトラストの信頼性を支える要因といえます。
最小権限の原則
ゼロトラストを導入・運用する企業や情報システム部門では、ユーザーに与える権限を必要最小限に制限する「最小権限の原則」が重要視されます。
これは、業務に必要なリソースのみにアクセスを許可することで、不正使用や情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための考え方です。
例えば、一般社員に人事情報システムへのアクセス権限が与えられていなければ、IDが悪用されても従業員の個人情報や評価データの流出を防げます。さらに、AIを活用してアクセス履歴を分析し、不要な権限を自動で見直す仕組みを構築することで、より効率的でセキュアな管理が可能になります。「アクセスは最小に、検証は最大に」、これがゼロトラストの基本原則です。
ゼロトラストの2つのメリット
ゼロトラストを導入することで、企業は単にセキュリティレベルを高めるだけでなく、柔軟な働き方の実現や業務効率の向上といったビジネス上の効果も期待できます。ここでは、下記の2つのメリットを解説します。
- セキュリティを強化できる
- 従業員の働きやすさを高める
セキュリティを強化できる
ゼロトラストのメリットの1つは、セキュリティを強化できることです。
ゼロトラストは、すべてのアクセスを検証する仕組みにより、従来の境界型防御では防ぎきれなかった内部からの脅威にも対応できます。
例えば、MFA(多要素認証)を導入すれば、ID・パスワードが漏洩しても不正アクセスを防げます。MFAは、認証時に追加の認証要素(スマートフォン通知や生体認証など)が必要な仕組みのため、パスワードだけでは突破されません。また、アクセス権限の制御により、万一侵害されても被害範囲を最小限に抑えることが可能です。さらに、システム全体のセキュリティ状態を定期的に評価し、脆弱性への対応を継続的に行うことで、最新の脅威にも対応できるセキュリティレベルの維持もできます。
MFAについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
従業員の働きやすさを高める
従業員の働きやすさを高める点も、ゼロトラストのメリットです。
ゼロトラストでは、ユーザーや端末の信頼性を常に確認する仕組みにより、MFA(多要素認証)、端末のセキュリティチェックを通じて、安全なリモートアクセスが可能になります。これにより、場所や端末を問わず柔軟な働き方を支援することが可能です。
例えば、従業員が拠点外や自宅からでも安全に業務システムへアクセスできるようになり、テレワークの推進と生産性向上につながります。また、ゼロトラストは業種や事業規模に応じて柔軟に設計できるため、企業の成長と変化に合わせて拡張できる点も魅力です。安全性を確保しつつ、業務のデジタル化や多様化を進めたい企業にとって、ゼロトラストは有効な選択肢となるでしょう。
ゼロトラストを導入したいが、「認証基盤の整備に自信がない」「社内のシステムがバラバラで難しそう」といったお悩みはありませんか?「JumpCloud」なら、SSO(シングルサインオン)やMFA、多様な端末管理をクラウド上で一元化でき、ゼロトラストの導入を効率的にサポートします。まずは「JumpCloud」で、自社に最適なセキュリティ基盤づくりを始めてみてはいかがでしょうか。
ゼロトラストの導入における課題
ゼロトラストは高度なセキュリティ体制を実現できる一方で、その導入には課題も存在します。ここでは、ゼロトラスト導入における下記の代表的な課題について見ていきましょう。
- 組織文化の変革が求められる
- 技術的な障壁がある
組織文化の変革が求められる
ゼロトラスト導入の課題の1つは、組織文化の変革が求められることです。
「すべてのアクセスを信頼しない」という考え方は、従来の「社内=安全」という前提に慣れた組織文化の中では、従業員にとって煩わしく感じられることがあります。ログインのたびにMFAを求められたり、利用できるシステムやデータが制限されたりすることで、業務がスムーズに進まないと感じてしまう場合があるからです。そのため、従業員がこうした変化に戸惑わないよう、導入前にはゼロトラストの目的や必要性を全社で共有し、「業務を守るための仕組み」として全社的な理解を深めることが大切になります。セキュリティを「個人の責任」ではなく「組織全体の方針」として位置づけ、従業員が主体的に取り組める環境を整えましょう。また、部門間の連携強化やセキュリティ教育を通じて、意識の変革を促すことも求められます。
技術的な障壁がある
技術的な障壁があることも、ゼロトラスト導入の課題の1つに挙げられます。
ゼロトラストの導入には、既存のIT環境との調整や再構築が求められることもあります。特に、レガシーシステムやオンプレミス環境を多く抱える企業では、対応に時間とコストがかかることもあります。
加えて、アクセス制御や暗号化、ID管理など多岐にわたる技術の統合が求められるため、自社に適した製品選定や段階的な導入がポイントです。まずは、PoC(概念実証)などで小規模に試しながら段階的に導入を進めるとよいでしょう。
ゼロトラストを実現するための5つの構成要素
ゼロトラストを実現するには、ユーザー、端末、通信、アプリケーションなど、すべてのアクセス要素を継続的に検証・制御する必要があります。ここでは、ゼロトラストを構成する5つの主要要素と、それぞれに関連する技術について紹介します。
ゼロトラストの構成要素と主な技術
| 構成要素 | 概要 | 主な技術 |
|---|---|---|
| エンドポイント(デバイス) | ネットワークに接続される全端末 | EPP、EDR、MDM |
| ネットワーク | すべてのネットワーク通信を信頼せず、継続的な検証を前提とする | SWG、SDP |
| クラウド | クラウドサービスへのアクセスを常に検証し、設定ミスや不正使用のリスクを軽減する必要がある | CASB、CSPM |
| アイデンティティ(ID) | ユーザーIDごとの適切な認証・認可が求められる | IDaaS、PAM、IGA |
| ワークロード | サーバーやクラウド上で稼働するアプリケーションやデータベースなど | CWPP |
1. エンドポイント(デバイス)
エンドポイントとは、ネットワークに接続されるPCやスマートフォン、タブレットなどの端末を指します。ゼロトラストでは、信頼できる端末からのみアクセスを許可することが原則です。不正端末のアクセス防止には、以下のツールの活用をおすすめします。
EPP(Endpoint Protection Platform)
EPPは、マルウェア対策やウイルス検知など、アンチウイルスとも言われる基本的な防御を担うソリューションです。近年はAI搭載の次世代型も登場し、未知の脅威にも対応できます。
EDR(Endpoint Detection and Response)
EDRは、EPPでは防げなかった攻撃を検知し、被害の拡大を防ぐ役割を持ちます。感染後のマルウェアや侵入した攻撃者の挙動を監視し、攻撃経路の特定や自動隔離・復旧など、インシデント発生後の対応を迅速化します。
EDRについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
MDM(Mobile Device Management)
MDMは、インターネット接続機能を備えた携帯端末やタブレットなどのスマートデバイスのリモートロック、アプリケーション制御など、企業が端末を一元管理するための仕組みです。端末の紛失・盗難時のリスクにも対応できます。
MDMについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
2. ネットワーク
ゼロトラストでは、すべてのネットワーク通信を信頼せずに検証するという考え方が基本です。従来のように「社内ネットワーク=安全」と見なすのではなく、内外を問わず常にアクセスの正当性を確認する必要があります。この考えを実現するためには、通信の可視化とアクセス制御が必須です。代表的な技術として以下が挙げられます。
SWG(Secure Web Gateway)
SWGは、インターネットアクセスを中継し、マルウェア配布サイトや業務外サイトへのアクセスをブロックするプロキシ機能です。クラウド型SWGなら、アクセス制限などのセキュリティポリシーを、社内外を問わずすべてのユーザーに一貫して適用できるため、リモート環境でも統一されたセキュリティ対策が実現できます。
SWGを含んだネットワークセキュリティソリューションであるSASEについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
SDP(Software Defined Perimeter)
SDPは、接続前にユーザーや端末を認証し、許可された相手だけにアクセス先を公開する技術です。「見えないネットワーク」を構築し、不正なスキャンや侵入を防止します。
3. クラウド
クラウドサービスの普及により、企業の業務環境はオンプレミスからクラウドへと大きくシフトしています。SaaSやIaaS、PaaSなどを活用するなかで、クラウド上のアクセスも常に検証し、信頼しない前提で管理することが求められています。クラウド環境のセキュリティを強化するには、以下の技術が効果的です。
CASB(Cloud Access Security Broker)
CASBは、クラウドサービスの利用状況を可視化・制御し、IT部門が把握していないクラウドサービスの利用(シャドーIT)や不正アクセス、情報漏洩などのリスクを低減します。クラウドの利用実態を把握し、個人情報保護法や社内ポリシーなどの規制・ルールを遵守する上でも有効です。
CSPM(Cloud Security Posture Management)
CSPMは、クラウド設定のミスや過剰な権限付与などを自動で監査・修正するソリューションです。セキュリティポリシーの適用や運用状況の継続的な評価を通じて、クラウド全体のセキュリティを維持します。
4. アイデンティティ(ID)
ゼロトラストにおいて最も重要な要素の1つが、ユーザーIDの管理と認証・認可です。誰が、どこから、どのようにアクセスしているかを正確に把握し、信頼性を検証することで、不正アクセスや内部不正を防ぐことができます。この領域で活用される主なソリューションには、以下の3つがあります。
IDaaS(Identity as a Service)
IDaaSは、クラウド上でID管理を行うサービスです。SSO(シングルサインオン)やMFA(多要素認証)などの機能を統合的に提供し、ユーザー認証を一元管理できます。「JumpCloud」のように端末管理まで対応した製品もあり、ゼロトラスト導入に適しています。
IDaaS、SSOについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
PAM(Privileged Access Management)
PAMは、特権ユーザー(管理者など)のアクセスを厳格に管理・監視するための仕組みです。操作ログの記録やアクセス制限によって、内部不正や情報漏洩リスクを抑えることができます。
なお、統合IDセキュリティサービスの「Silverfort」なら、既存のインフラをほとんど変えずに特権アクセスのセキュリティを強化することが可能です。
IGA(Identity Governance and Administration)
IGAは、IDと権限のライフサイクル(付与・変更・削除)を管理・統制する仕組みです。人事異動などに応じて自動的に権限を更新し、不正なアクセスを未然に防ぐとともに、社内ルールや法律の遵守といったコンプライアンス対応にも役立ちます。
5. ワークロード
ワークロードとは、業務で利用されるアプリケーションやサービス、データベースなど、クラウドまたはオンプレミス環境で動作する処理の単位です。これらは企業の中核業務を支える一方で、サイバー攻撃の対象となりやすい領域でもあります。ゼロトラストでは、ワークロード単位でアクセス制御や検証を実施することで、セキュリティを強化します。
その際に有効なのが、クラウドや仮想環境で稼働するワークロードを保護するためのプラットフォームであるCWPP(Cloud Workload Protection Platform)です。
CWPPの主な機能
- 仮想マシンやアプリケーションの構成管理
- 脆弱性の検出と修正
- 通信の可視化とマイクロセグメンテーション(細分化)
- シャドーITの検出と制御
CWPPは、IaaSやPaaSといった異なるクラウド環境を横断してセキュリティ対策を統合管理できるため、運用負荷の軽減と保護レベルの標準化に役立ちます。また、ワークロードを個別に監視・管理することで、ゼロトラストの原則にもとづいた緻密な防御体制を構築可能です。
このようなCWPPの要件を満たす製品の一例として、「SentinelOne」が挙げられます。「SentinelOne」は、エンドポイント検知・対応(EDR)の機能を備える一方で、CWPPとしても活用でき、複数のクラウドサービスプロバイダーを組み合わせたマルチベンダーのIaaS上で稼働するサーバーを保護します。
ゼロトラストで進化する情報セキュリティに対応しよう
ゼロトラストは、巧妙化するサイバー攻撃に対応するための新たなセキュリティモデルとして注目されています。「すべてのアクセスを信頼しない」という前提に基づき、業種を問わず導入が進んでいます。このモデルでは、ユーザーや端末、クラウドなどすべての要素を継続的に検証・制御することで、不正アクセス、情報漏洩のリスクを抑え、業務の安全性を高めることが可能です。
一方で、導入には技術的知識、組織的な理解、段階的な設計と実行が求められます。ID管理には「JumpCloud」、エンドポイント対策には「SentinelOne」、ネットワークには「Check Point Harmony SASE」、特権アクセス管理には「Silverfort」など、信頼できる製品を組み合わせ、自社の優先領域から段階的に導入を進めるアプローチも効果的でしょう。
ゼロトラストは、単なるセキュリティ強化にとどまらず、企業の信頼性向上と持続的成長を支える情報戦略の一環です。今こそゼロトラストの導入を本格的に検討してみてはいかがでしょうか。





